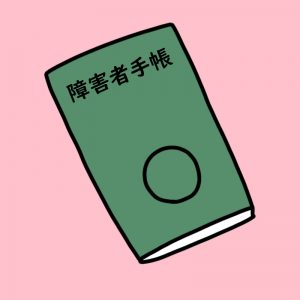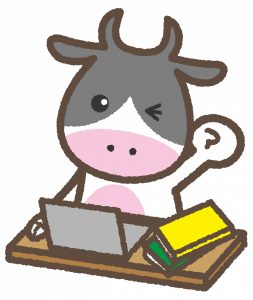和服から洋服への時代
エナベル水戸駅南就労A利用者のSCです。
ブログの訪問ありがとうございます。
筆者は、キュレーターではありませんが、個人的趣味で博物館・美術館に行くのは好きです。
行って参りました(^-^)水戸市立博物館
あらためて紹介すると・・・
■特別展 洋服と和服の100年
会期:令和7年10月25日(土)~11月30日(日)
会場:水戸市立博物館(水戸市大町)4階/5階展示室
開館時間:9:30~16:45(入館は16:15)
休館日:月曜日及び11月4日(火)・25日(火) ※11月3日(月祝)24日(月振)は開館
料金:一般200円(団体20名以上150円)着物の方割引あり(ご確認ください)
18歳以下65歳以上・障害者手帳保持者/付き添いの方1名無料
(茨城県民の日(11/13・ハッピーホリデー(土日祝18歳以下のお子様付き添い1名無料)
着物の方割り引きと言われても・・着物で出かける気力はなく・・
ですが筆者の出掛けた15日(土曜日)は、比較的温かな日。帯付きで出かけても丁度良い感じでした。
因みに、水戸駅観光案内所で、招待券ありの文字を発見しました。
さて、内容はと言いますと・・・
80年ほど前までは和服が一般的な衣服でした。
現在のように洋服になったのは昭和30~50年代になってからでしょうか?
既製服が大量生産されるのも昭和40年代前後から、それ以前は家庭で手作りしたり、洋裁が出来て近所でミシンを持っている人に頼んで、縫ってもらいました。
その頃は、洋裁を習うための裁縫学校も全国で多数開校していました。
明治以降の女学校等でも裁縫教育が行われていました。
戦後、既製服が大量生産される流れの中で、多くの洋裁学校がなくなってしまいました。
日本人の衣服がどのように移り変わっていったのか、実物の資料や当時の写真を交えて、その経緯を追い、併せて戦前から戦後の水戸の学生の服装などが展示されています。
世代によって、感想はそれぞれでしょう。リアル世代の方は「懐かしい、そうそう!」と感じることでしょう。
筆者世代はついていけるし、「洋服着てる!」と言われた時代から「着物着てる!」という時代の流れ・・・を感じ取ってください。
男子中学生(旧制)はまだまだエリートの時代とはいえ、写真の中の男子!かっこいいです。
あとは、ドレメと文化の違い(洋服の原型のおこし方)、βとVHSの違いか?ブルーレイとDVDの違いか?(これすらもう古いけど)む歴史を感じます。
関連行事としていくつかのイベントがありましたが、終わってしまいまっています。
まだ間に合うのは:
●11月23日(日・祝)14:00~のギャラリートーク(担当学芸員)が4階展示室で(参加は無料ですが入場券は必要)行われます。
●2階ロビーでワークショップ(無料)折り紙によるドレス作成できます。(私が言うのもなんですがお気軽にどうぞ)
さて、ライブラリアンとして本のご紹介
■「エレガンス」石川智健 河出書房新社
たまたま、偶然に最近読んだ本です。
ちょっと勘違いして・・・タイトルから戦争中に(おしゃれ禁止の時代に)なんとか工夫し、きれいになりたい話・・を想像したら、違ってました(-_-;)
空襲が激化する1945年1月、警視庁でただ一人、ライカのカメラを扱える石川光陽。
写真室勤務である彼の任務は、戦禍の街並みや管内の事件現場を撮影すること。
女性四名の連続首吊り自殺が報じられていて、四人は全員、珍しい洋装姿で亡くなっており、花のように広がったスカートが印象的なため“釣鐘草の衝動”と呼ばれ話題に・・・
警視庁上層部から連続する首吊り事件の再捜査命令が光陽に、彼と組むのは内務省防犯課の吉川澄一。
自殺説の中、吉川は他殺を疑い・・・
犯人は・・・
個人的感想としては、推理小説としてみた場合に犯人の意外性と動機は今一つ・・(最初犯人と思った人は全く関係なくいい人でした、疑ってごめんなさい)
ある意味犯人はサイコですが、もう少し壊れていてもいい感じ?
この本を紹介したのは、丁度被害者がドレメの生徒さんだから、戦争中の洋裁事情が比較できます。
石川光陽氏は実在の人物です(平成元年に亡くなっています)
東京大空襲の悲惨な写真を撮影しGHQからフイルムを守った方。この小説とは別に、ドラマ化されて、中村トオルさんが演じています。
空襲のシーンが悲惨で(殺害現場の描写より)読んでいて本当に辛いです。
博物館と小説1冊よろしければチェックしてみて下さい。
青字は市立図書館でりました。
エージレスの段ボールが、うず高く積まれていて、ツインタワーのようです。
エージレスの封入この後励みます。
一週間始まったばかり、頑張りましょう(^^)/